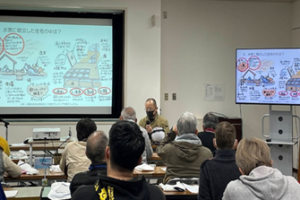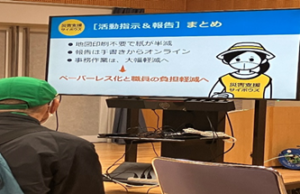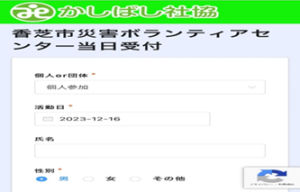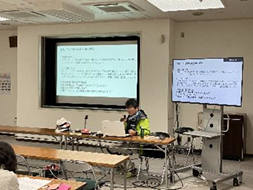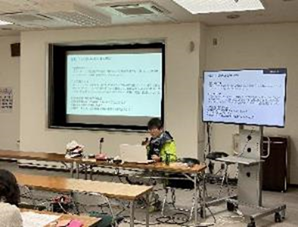能登半島地震への支援活動について
1月13日に開催した理事会で能登半島地震への取組みを以下のとおり行うことを決定しました。
県防災士会としては、当面の支援活動は被災地で頑張っている石川県支部への支援を中心に行う。
具体的には、
1,現予算の中から20万円を石川県支部へ送る。
2,県防災士会として、統一行動日を設定する。
①2月9・10・11(土・日・祝)
②3月9・10(土・日)
③3月16・17(土・日)
但し、具体的な行動内容は、県内一斉の寄付・募金活動となるか、災害ボランティアの派遣とするかは現地の状況に合わせて検討となります。
あらためてホームページにてお知らせします。
会員の皆さんにおかれましたは、この統一行動日の日程をあけておいて下さい。
3、石川県支部から支援者要請(募集)が届いています。
主な活動は、被災地での避難所支援活動で、完全自己完結型の募集となります。
_募集条件を確認の上_、参加できる方は事務局まで連絡をお願いします。(詳細や申込方法については改めてホームページで案内します)
参考:石川県支部臨時掲示板 https://bousaishikai17.blog.jp/2024.01.10支援者募集の公募(石川県支部)