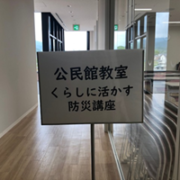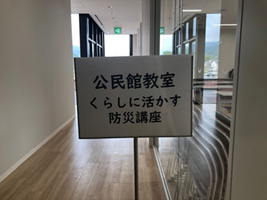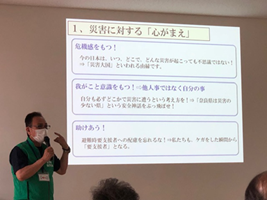防災とボランティアのつどい
奈良防災プラットフォーム連絡会より、JVOADよりの案内がありましたのでお知らせします。
【ご案内】 防災とボランティアのつどい 2月6日(日)13:30~16:00
都道府県域ネットワークご関係者の皆様
お世話になります。JVOADの鈴木です。
本日は 「令和3年度 防災とボランティアのつどい」のご案内でご連絡させて頂きました。
「防災とボランティアのつどい 能登半島地震・新潟県中越沖地震からボランティアの連携・協働を考える」が、2月6日(日)にオンラインで開催されます。
JVOADからも、代表理事の栗田ならびに事務局長の明城が登壇いたします。
以下、プログラムの概要、申込方法となりますので、ぜひご参加ください。
令和3年度防災とボランティアのつどい
───────────────────────────────────
能登半島地震・新潟県中越沖地震からボランティアの連携・協働を考える
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/index.html
───────────────────────────────────
【日時】令和4年2月6日(日) 13:30-16:00
【開催方法】オンライン開催(Zoom)
※申込された方に後日Zoom IDをお送りします。
【主催】内閣府
【参加費】無料:どなたでも参加いただけます(事前申込制)
───────────────────────────────────
▼趣旨
発生から15年を迎える「能登半島地震」、「新潟県中越沖地震」を振り返り、
支援者によってどのような連携・協働が進められてきたのか、被災地で尽力された方からお話をお聞きするとともに、これからのボランティア活動について話し合う機会としております。
▼参加お申し込み
ウェブサイトよりお申し込みください。
http://dynax-eco.com/form/tsudoi2022/
※フォームに「参加方法」の項目がございますが、
新型コロナウイルス感染拡大を、完全オンライン参加となりました。
「オンライン(Zoom)参加」を選択ください。
───────────────────────────────────▼ご登壇者(予定)
第1部
・稲垣文彦氏(公益社団法人中越防災安全推進機構理事)
・村田明日香氏(石川県社会福祉協議会)
・栗田暢之氏(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)代表理事)
第2部
・中原敦子氏(社会福祉法人新潟県社会福祉協議会地域福祉課長)
・李仁鉄氏(にいがた災害ボランティアネットワーク理事長)
・佐藤貴規氏(上越市社会福祉協議会地域福祉課地域福祉係)
・明城徹也氏(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)事務局長
・萩原玲子氏(内閣府 政策統括官(防災担当)付 企画官(普及啓発・連携担
当))
【お問合せ先】
防災とボランティアのつどい事務局
株式会社ダイナックス都市環境研究所 担当 津賀・細川
〒105-0003東京都港区西新橋3-15-12 GG HOUSE 5F
TEL :03-5402-5355 FAX :03-5402-5350