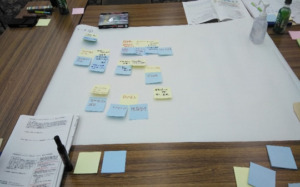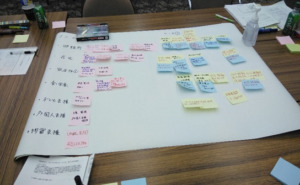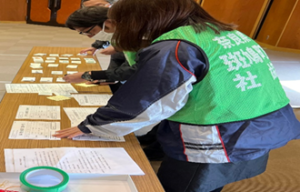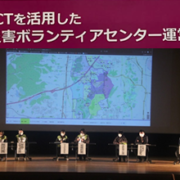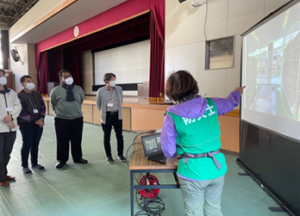明日香村での災害被災者支援ボランティアを募集
緊急の災害ボランティアの募集です。
県社協から明日香村での災害復旧支援への協力依頼がありました。
奈良県防災士会から有志が現場で活動しておりますが、県社協のボランティア募集が
7月17日(月)まで延長となりましたので、緊急ではありますが災害ボランティア活動に参加できる方を募集します。
<とき>
①7月13日(木)、9時~16時
②7月15日(土)、9時~16時
③7月16日(日)、9時~16時
④7月17日(月)、9時~16時
<ところ>
明日香村稲渕地区
<現状>
床下の泥出しは大方終わりましたが、まだ他の部屋の下に泥が堆積している状態です。レスキューアシスト 中島さんが指揮を執り、作業を進めます。
<参加申込>
奈良県防災士会事務局までメールで申し込み下さい。
mail@bousainara.com
<集合場所>
奈良県防災士会から団体参加の方は、明日香村「太子の湯(村社会福祉協議会隣接)」の南西側の駐車場に集合して、参加者確認後、各自の車で指定駐車場所へ向かいます。
※必ず事前申込をお願いします。
<その他>
資機材は、村社協が用意します。
<注意事項>
「ボランティア活動保険」は、あらかじめお住まいの社会福祉協議会で加入してください。
当日の保険加入は出来ません。必ず前日までに加入して下さい。
※未加入の方は、作業できません
(先日、奈良県防災士会で募集した「ボランティア登録」をされた方は保険加入済みです)
明日香村でボランティアセンターが立ち上がっています。
活動期間は7月17日(月・祝)までとなっております。
※事前申し込みとなります。
<ボランティアが初めての方へ>
災害ボランティアが初めての方へ、持ち物・装備(一例)を記載しました。
服装:長袖(乾きやすい繊維)、長靴,、保険証、タオル、帽子またはヘルメット、マスク、厚手のゴム手袋など
持ち物・食べ物・飲み物全て自身で用意し、参加をお願いします。
昼食は持参ください。かなり汗をかきますので、ポカリなどの水分を多めに持参をお願いします。
雨天の場合も作業がありますので、雨具等の用意をお願いします。