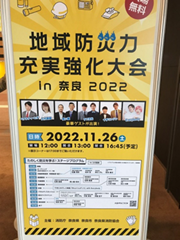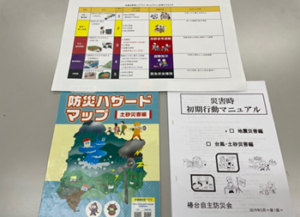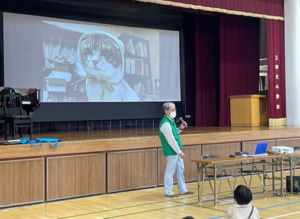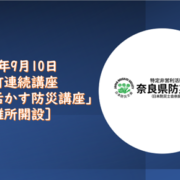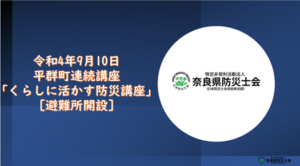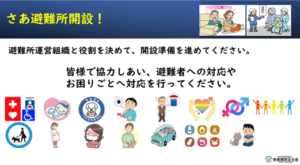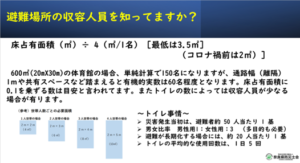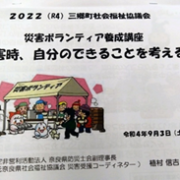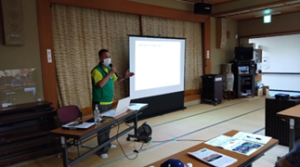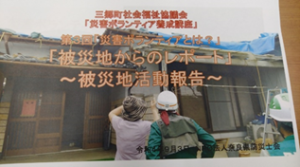天理市西長柄町防災訓練
令和4年11月20日(日)天理市西長柄町公民館及び長柄第1公園において、西長柄町自治会・自主防災会主催による「西長柄町防災フェア」が開催されました。第5回となる今年の防災活動フェアは奈良県の「地域防災力支援ワークショップ・自主防災訓練支援事業」の支援を得て行われ、約180人が参加しました。
自主防災会の班員は所属する「総務避難誘導班」「水防消火救護班」「給食給水班」のそれぞれに定められたテーマに沿って訓練を行いました。総務避難誘導班は「安否確認用シート」を用いて全世帯の安否確認を行い、その集計を災害対策本部へ報告しました。水防消火救護班は安否確認のサポートと、天理市消防分団の指導による「初期消火訓練」を行いました。給食給水班は「レトルトカレーの提供」を150食行いました。防災倉庫の備品をすべて搬出して「防災備品展示」も実施されました。
参加者は奈良県防災士会の板垣防災士と村山防災士による「安否確認の取組みについて」の講演を聴講した後、奈良県防災士会の指導による「簡易担架」「ロープワーク」「簡易トイレの使用方法」などを体験しました。
(報告:南上防災士)