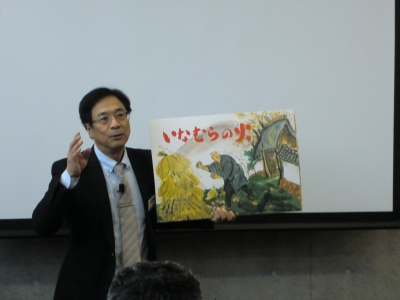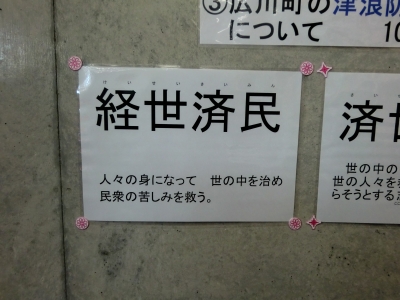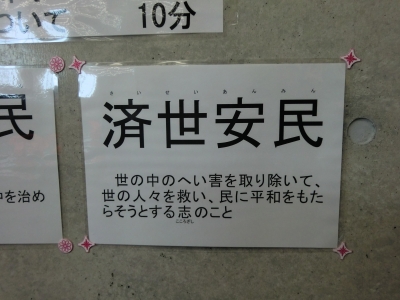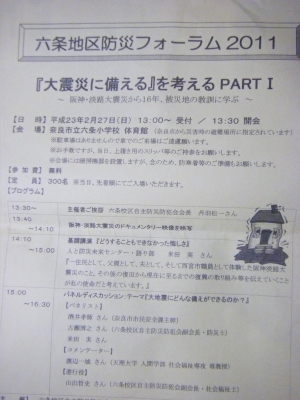防災士シンポジュームin姫路
阪神・淡路大震災、東日本大震災や台風12、15号の教訓を踏まえて、東海・東南海・南海地震などの巨大地震に備えるための課題を抽出し、市民レベルにおける防災・減災への取り組みの方向性を示すべく、下記の日程で「防災士シンポジューム」が開催されます。
防災士の皆様におかれましては、積極的な参加をお願いします。
◇ 事業名称 第3回 防災士シンポジューム in HIMEJI
◇ 開催日時 平成24年1月29日(日)、13時~17時
◇ 入場料 無料
◇ 主 催 NPO法人 日本防災士会兵庫県支部
◇ 協 賛 NPO法人 日本防災士会、日本防災士機構
◇ 主な内容
13:00 開会
13:20 基調講演 「大震災の教訓を地域にどう活かせていくか?」
14:30 パネルディスカッション
「大震災の教訓を活かす地域防災リーダーの役割」
● コーディネーター
大石伸雄(防災士会兵庫県支部長)
● パネリスト
藤原由成(兵庫県西播磨県民局長)
有馬妙子(姫路市連合婦人会長)
橋本 茂(日本防災士会専務理事)
梅木直幸(防災士会和歌山県支部長)
16:50 閉会あおさつ
17:00 閉会
◇ 申し込み 氏名・住所・連絡先を記入の上、
〒 671-1511
兵庫県揖保郡大田768-5
ジンポジューム事務局(森川)まで
Eall mtbousaisi@yahoo.co.jp
FAX 079-277-4770

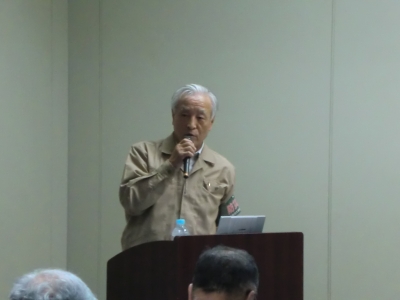
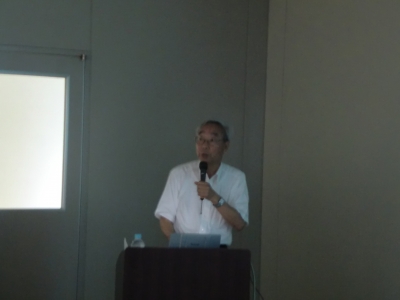
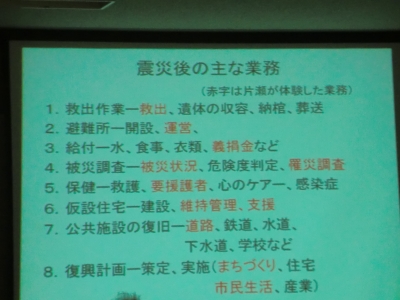
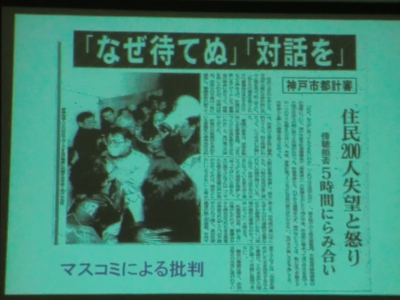

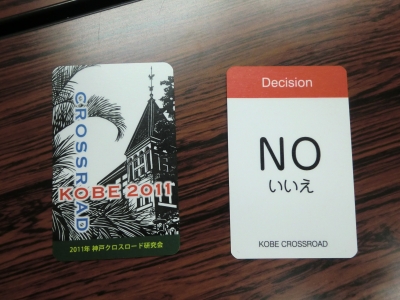



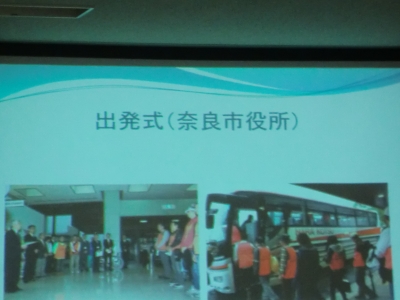
 後日、報告書は全文ホームページに掲載します。
後日、報告書は全文ホームページに掲載します。