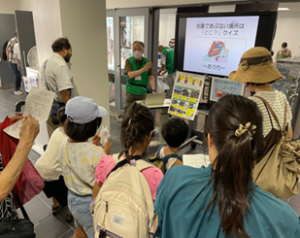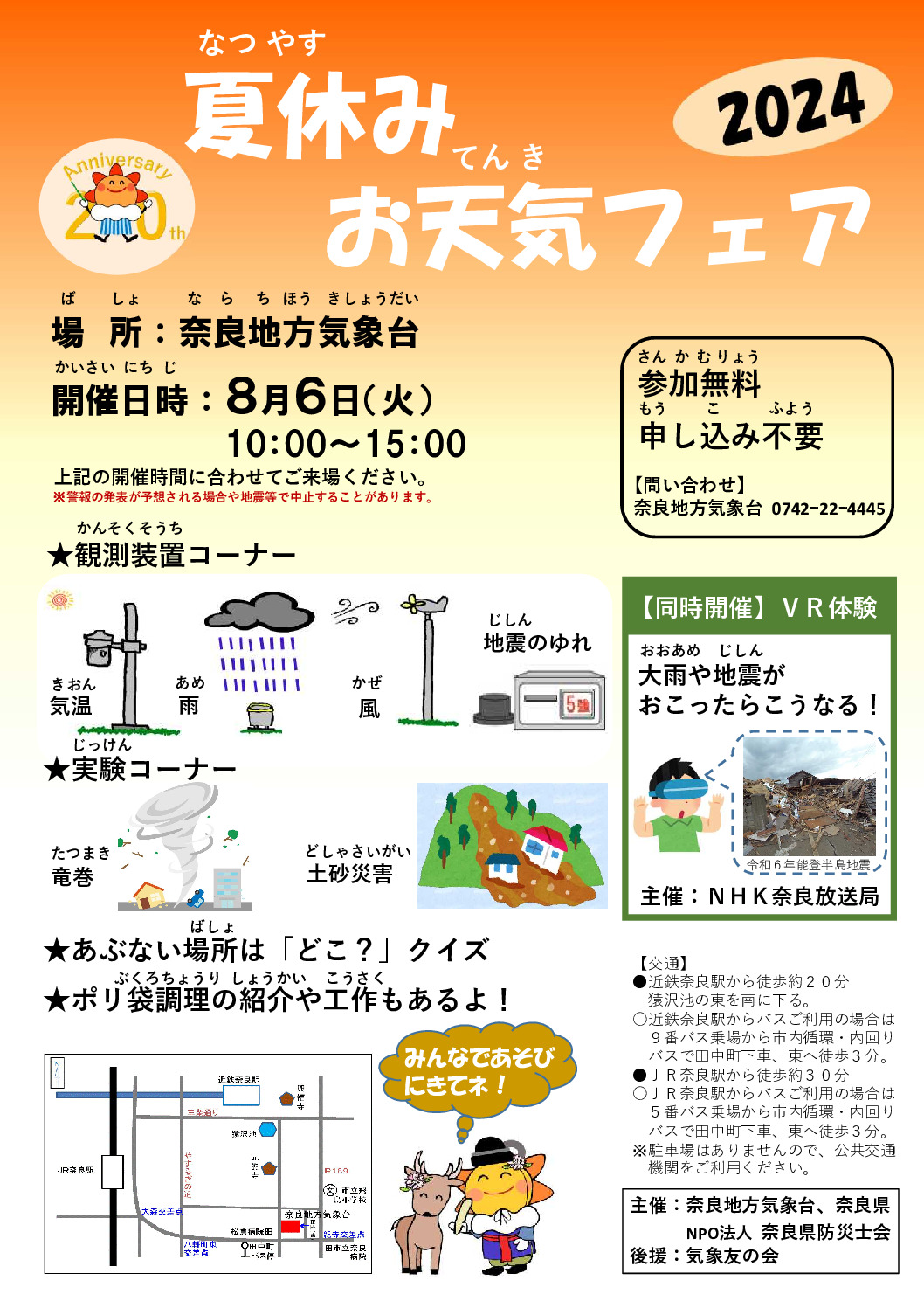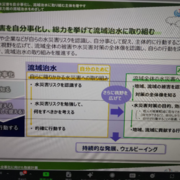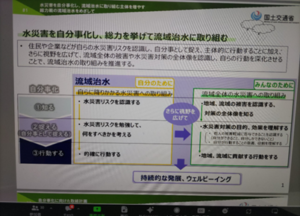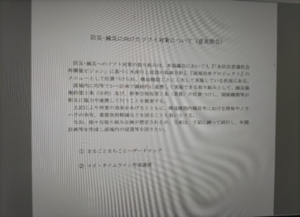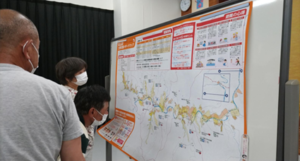2024年9月13日、能登半島地震第7次被災地支援活動の防災士8名のメンバーが近鉄西大寺駅南側ロータリーに集まり21:50頃出発しました。今回がNPO法人奈良県防災士会としての能登支援活動は最終となります。参加メンバーの自家用車5台に分乗して石川県珠洲市を目指しました。
14日(土)5:20頃に順次道の駅すずなりに到着。そこで朝5:00から営業していた「すずキッチン」で昼用のお弁当を購入して各自車内で仮眠。7:45頃、珠洲市ボランティアセンター(以下VC)へ向けて移動し到着後、スマートフォンでの受け付け登録を行い、活動先の説明と他からのボランティアの方とマッチング、オリエンテーションを受けました。午前は奈良県防災士会メンバーは4名ずつ北村班と大坂間班に二手に分かれ、それぞれの依頼先へ向かいました。北村班メンバーは川口、湯浅、福本の各防災士とひのきしんの方2名と行動を共に飯田へ向かいました。飯田地区1件目は「仏壇、畳の運び出し」の依頼で、家人の立会いのもと引き戸や小型冷蔵庫、照明器具や小物も廃棄を要望され回収して運び出しました。津波で被害を受け母屋は地盤が隆起し、リフォームしてまだ7年ほどでローンも残っているとおっしゃってましたが取り壊しを決めたとの事。依頼の完了をご確認いただきひとまずVCへもどり報告。
時刻が10:00とまだ早いため飯田地区での2件目を受諾。以前、小料理屋だったお宅の取り壊し前の片づけ作業で前回作業のボランティアが廃棄し忘れたものが残っているということでシンクや裏庭の植木鉢などを回収しました。植木鉢は土嚢袋に入れ叩き割って回収。母屋の中はまだ手つかずで、VCでの報告では今回で依頼は完了、ただ今後も要対応と報告した。VCの受け付けの方から「今後についてこちらからよく調べておきます」と対応いただきました。
一方、宝立地区へ向かった大坂間班、村山、吉川、矢作各防災士は加賀の防災士2名との行動でした。納屋の中に大量の物があり、祭の準備のために運び出してほしいという依頼で、立ち会い人不在の為、自己判断しなければならない案件でした。実際にはひどい有様でトラクターの関連部品、細かい廃棄物や蜂の巣やネズミがいたりと大変だったとのことで、全員ここでの作業でかなり疲弊した様子でした。
昼食のお弁当をVCのテント下でいただいたのち、午後からの案件へ出発。
宝立地区の現場に13時過ぎに到着。今回2回目で納屋の分別したゴミを運び出す作業で依頼主の高齢の女性から説明を受けました。15年前に先立たれた左官業のご主人が、納屋に貯め込んだらしい色々なものをまとめて廃棄したいとのことでとにかく軽トラに載せ集積場へ。家庭ごみに判断されるかと思ったら可燃ごみは家具類の災害ごみとして全て回収されたとのこと。他には木切れ、木材が大量にあり2台目のトラックへ載せ集積場へ運びました。母屋内はまだ手つかずでしたが集積場の受け入れ時刻に間に合わないため、依頼主さんとお話をして今後してもらいたいことを聞き出し、その内容を要継続としてVCに報告しました。1日目はとにかく暑く汗を多くかいた1日でした。
報告完了後、防災士会に翌日お願いしたい依頼があるということで内容を確認したところ、折戸地区の納屋の片付け作業で8人で向かうこととなりメンバーにも共有したのちVCを出発。その日の宿泊を予約している能登町の「少年自然の家」へ向かいました。奈良県防災士会が何度もお世話になっている野外活動施設で復興支援の業者の方も宿泊されていました。
翌日の9月15日、未明から雨が降っていました。7時半ごろに珠洲市VCに着いたころは少し晴れ間があり涼しい感じでした。オリエンテーションも割愛され奈良県防災士会8名全員で目的地の折戸の「木ノ浦海域公園」へ向かいました。依頼内容は「納屋の使わなくなった漁の網をハサミで切って鉛の重りを回収し分別して欲しい」というものでした。海沿いの綺麗な湾に面した場所で震災前にはカフェもあったようですが被災し取り壊されていました。朽ちた納屋の中に漁具があり、これまでのボランティアの継続活動として各自でハサミを持って景色を眺めつつひたすら網から重りをハサミで切り取る作業を行ないました。空は次第に曇天となり、村山防災士から思わず「鉛色の空の下で鉛を切り取る作業とは」というセリフが出ました。雨雲情報がやばいと何人かが言い出しカミナリが鳴り始め瞬く間に土砂降りの大雨となりスマートフォンからは土砂災害警報も出始めたため作業を中断して雨宿り。この日は夕方まで雨予報となっており雨脚が小康状態になったところでVCに確認の連絡を取り撤収としました。VCで作業の報告をし終わったのが11時半でこの時点で奈良県防災士会としての能登半島地震被災地支援活動の終了としました。
なお気になる珠洲市VCの運営については10月からは土日など週末に限定した開設へと移行するとの事。平日のボランティアがほとんど来なくなったからだそうです。奈良への帰投の前に道の駅すずなりに隣接された「すず食堂」へ立ち寄って皆で昼食を取りました。珠洲市内の被災した4つの飲食店さんが合同で開業された食堂とのことで、ボランティアや地元の方々で列が出来るほど賑わっていました。復興にちなんで「福幸丼」と名付けられた福を呼ぶ海鮮丼をいただきましたがとても美味しかったです!道の駅すずなりも多くの人が訪れ、珠洲は元気で復興は時間は掛かっても着実に進んでいるんだなと感じさせられました。メンバーは22時過ぎに近鉄大和西大寺駅前へ到着、解散となりました。
参加防災士
大坂間弘明(上牧町)
村山央(広陵町)
川口均(生駒市)
矢作一(奈良市)
福本学(奈良市)
吉川和伸(生駒市)
湯浅茂雄(大和高田市)
北村厚司(三郷町)
以上8名、皆様たいへんお疲れさまでした。
報告:北村防災士