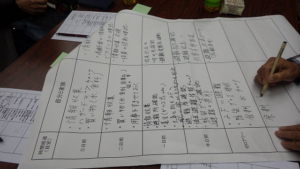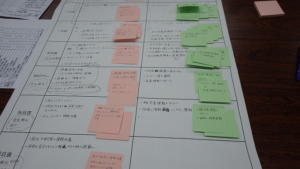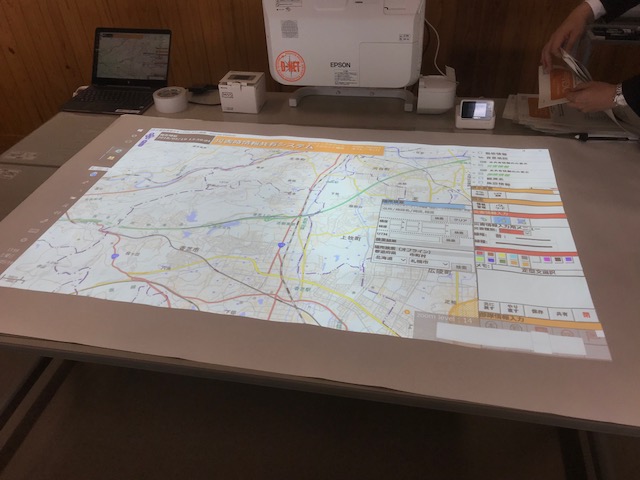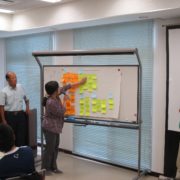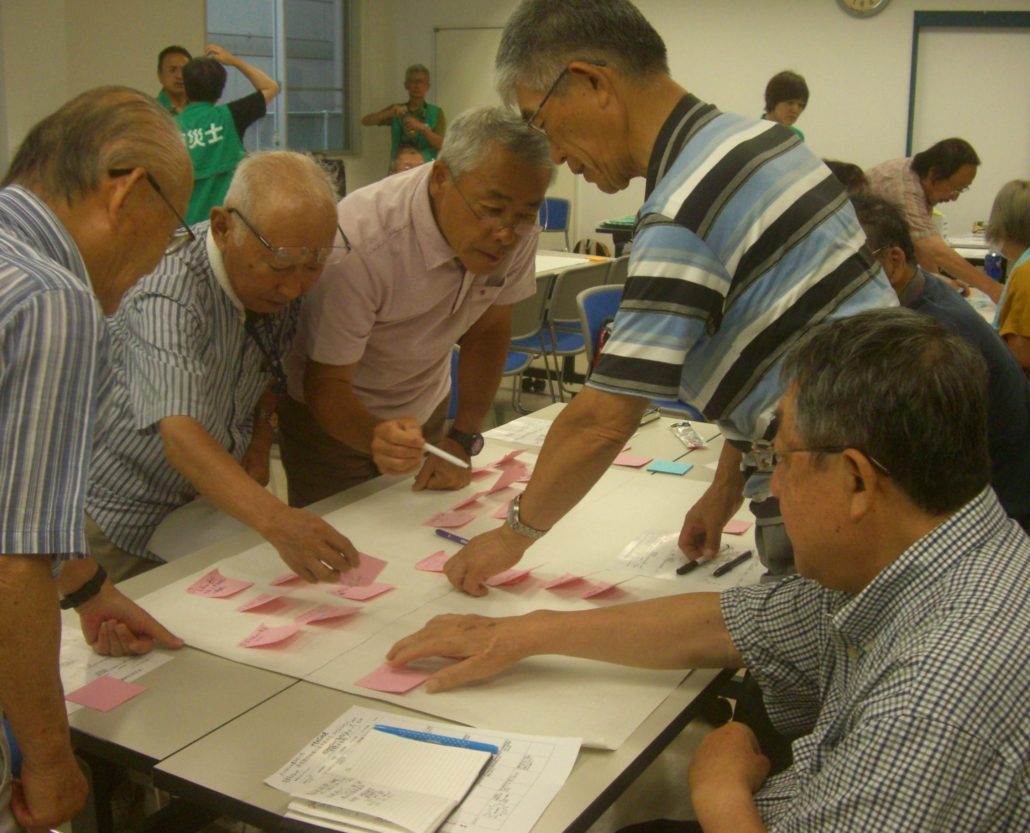大宇陀小学校防災訓練
11月12日(火)に、宇陀市大宇陀小学校において、夏季休業中の教職員研修会に引き続き、児童・保護者向けの防災講演を行いました。 当日は、①児童・保護者が体育館に集まり児童向けのお話。②児童が教室に戻ったのちに保護者向けの講演。③保護者参加のもと、学校の引き渡し訓練 の順で行われました。 児童向けのお話では、阪神淡路大震災の映像(コンビニなどの陳列物が崩れ落ちる様子など)を見た後、何人かの児童に前に出てきてもらい、教室や下校中のブロック塀脇などで地震に遭った時のシェイクアウト訓練を行いました。教室を想定した場面では日ごろの学校での訓練の成果が表れていましたが、通学路を想定した場面ではブロック塀を想定した段ボールの下敷きになってしまいました。改めて児童全員で地震に遭遇した場所での対応のポイントが確認できました。 保護者向けの講演では、『家庭ですべき災害への備え』と題し、自分自身や家族を守るために知っておくべき〈地震や水害に関する知識〉〈「避難」の考え方〉〈日ごろの暮らしの中でできる備え(寝る時、かたづけ、買い物)〉について情報を共有し、「命を守る」ということについて考えました。 大宇陀小学校では初めてとなる、保護者参加の引き渡し訓練。これまで先生方で数回シミュレーション訓練を行ってこられたこともあり、想定した手順で大きな混乱なく進みました。 すべての予定が済んだあと、校長先生、防災教育担当教員、防災士が集まって、防災士より訓練についての講評・課題等についてお伝えし、学校の今後の進め方について意見交換を行いました。引き渡し訓練についての保護者アンケートを踏まえ、今後も訓練を積み重ね、課題を整理して次に活かす、いわゆるPDCAでより有効な防災教育が実施されていくことでしょう。 (報告者:岡本防災士)