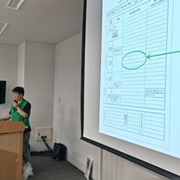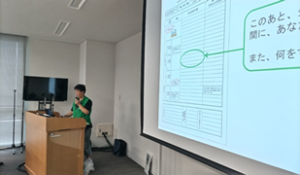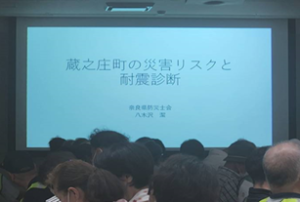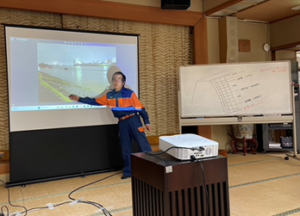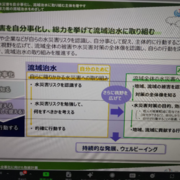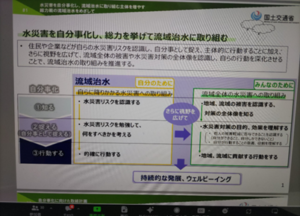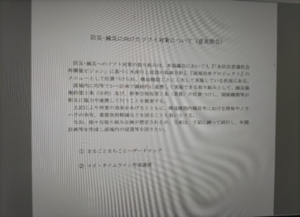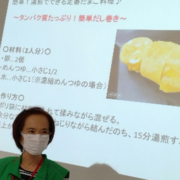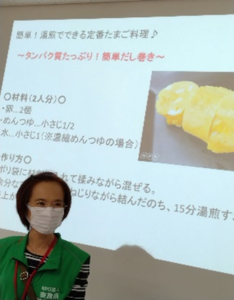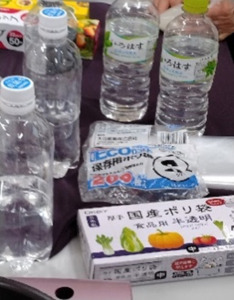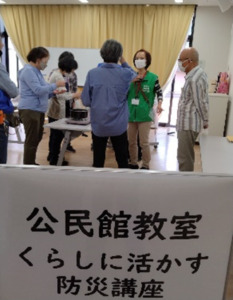令和6年能登半島地震第9次災害ボランティア(10月14日~17日)
令和6年10月14日(月祝)から17日(木)まで、石川県珠洲市災害ボランティアセンターを拠点に活動を行いました。今回奈良県防災士会は八木沢1名での参加であり、他の団体とコラボしての支援活動でした。
(活動日とコラボした団体)
10月14日(月祝)チームふくいとのコラボ計10名 10月15日(火)北陸電力の2名とのコラボ計3名
10月16日(水)ボラキャン3名・北陸電力2名とのコラボ計6名 10月17日(木)ユネスコ5名とのコラボ計6名
(現地の状況)
地震被害の公費解体が進み、週末のみにボランティアセンターを縮小しようとした矢先に広域水害発生。川の近くのお宅は浸水被害、山の麓のお宅は土砂被害となっていた。地震被害に水害・土砂被害が加わる多重被害となっており、住民さんの疲労の色も濃くなってきています。
(支援内容)
震災被害を受けたお宅の家財の運び出し。また土砂被害を受けたお宅へは泥だしが主な作業でした。
(4日間の活動を通して)
珠洲市ボランティアセンターには、平日にも関わらず100名を超えるボランティアが来ていました。石川県のボランティアバス2台、福井県から「チームふくい」のバスが毎日運行。ボラキャンも毎日数名が参加。土砂被害を受けたお宅では床板はがしが終わっていないお宅も多く、レスキューアシストや他の技術系ボランティアが先に床板をはがし、その後に一般ボランティアが泥だしする工程となっていました。その泥だしをまだ20代の若者がどろどろになりながらも、積極的に行っている姿を見て頼もしく感じました。16日夜の宿泊を、石川県防災士会のご厚意で「蛸島町第1団地」(仮設住宅)集会場をお借りできました。前の週に植村相談役と村山さんが宿泊された所と同じ場所になります。住民座談会の内容が壁に掲示してあり、仮設住宅に住まわれている方々の苦悩が書き記されてありました。今回の活動は、毎日ボランティアセンターを立ち上げてくれた珠洲市社協職員の方々、コラボさせて頂いた各団体の方々、毎日お弁当を販売してくれたすずキッチンの方々、宿泊手配頂いた石川県防災士会、ボランティアを優先的に宿泊させて頂いた和倉温泉「大観荘」の方々、後方支援をしてくれた奈良県防災士会の仲間があって無事に活動ができました。この場をお借りし深く感謝いたします。
(今後の予定)
奈良県防災士会として、今後も能登への支援活動を継続します。募集した際には皆様参加の程よろしくお願い致します。 <報告 八木沢 防災士>