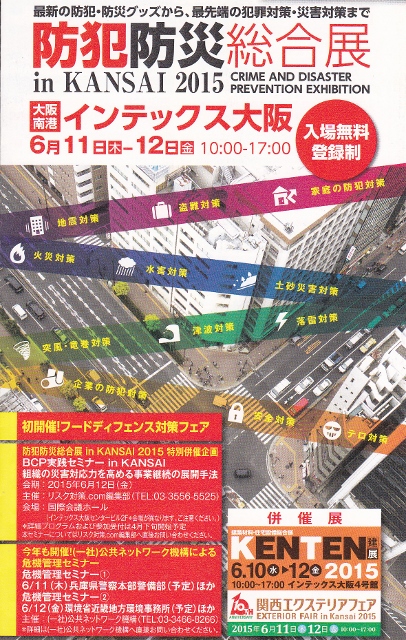「平成28年熊本地震」益城町災害支援活動報告
平成28年5月13日(金)午後9時に集合。奈良県防災士会11名、大阪府支部1名、一般参加者2名を加え、計14名の有志で橿原市役所前を出発、今回震度7の地震で被災した熊本県益城町に向かいました。 翌朝午前8時過ぎに、国道443号線沿い、秋津川支流の益城町辻の城地区公園内に、テントで設営された日本防災士会の災害対策支援本部に到着しました。
そちらでは、日本防災士会本部・防災士会熊本県支部・九州ブロック防災士会・防災士会岐阜県支部の防災士が活動されていました。この地区の災害支援は、防災士会が受け持たれ、町内からのボランティア要請の対応聞き取り、そして作業活動をされていました。
午前9時から今回の地震から1ヶ月が過ぎ、犠牲になられた方々に黙祷。そして、挨拶と地域の状況、作業内容を打ち合わせし、当日気温上昇の為水分補給、適時休憩、余震の警戒を確認。作業は、作業班①・②・瓦礫搬送班で編成。
(14日午前)
①班 家屋の前庭の土砂流出防止のため、植栽撤去・土のう作り・延長5mの土のう3段積み。
家屋東側落下瓦の袋詰め・撤去。
②班 家屋内の家具搬出・清掃、落下瓦の袋詰め・撤去。
搬送班 地区内巡回、積込み、町の瓦礫集積場へ搬送。
(14日午後)
①班 赤の張紙の家屋内、台所のタイル・落下壁の搬出、片付け。
黄の張り紙家屋の家電搬出、廃棄家具の積み込み。
②班 赤の張紙家屋内の家具搬出・清掃、落下瓦の袋詰め・撤去。残りの①班も合流。
搬送班 多量の瓦礫土のう・家具の人力による積込み・積下ろし搬送のため、メドのついた①班から3名応援、合計7名で最初は先導車の後をつけて、瓦礫を集積場へ運搬。 依頼者家屋の確定も困難、色々な要請が入る中、段差のある道を集積場へ3往復しました。
(15日)
昨日から続く、大量のガレキ瓦のため、家屋敷地内のガレキ瓦搬出の残り作業に、①・②班・
輸送班と東京からの一般ボランティアの方2名も加わり、安全を確認し、手作業によるガレキ瓦の袋詰めと搬出作業を全員で行った。
途中、屋根の雨漏れ防止の依頼がある家屋に、対策支援本部の高野隊長と、こちらから有志4名が向かい、平屋建ての屋根に登り、7m各のブルーシートを更に張り加え、土のうを積み、ロープで補強しました。(指示を受けた本部の高野防災士は、東京のホテルニュージャパン火災の時、多くの方の人命救助を為された元消防士さんです。)
支援本部では、安全確認した上で、重機による道路のガレキ撤去も行っておりました。
予定の作業終了後、日本防災士会熊本県支部長の宮下正一さんの同行で、震源地付近とされる益城町役場、避難所のある益城町総合体育館、屋外での支援物配布、亀裂の走る断層帯を視察させて頂き、その後夕方には熊本県を離れました。
14日の小国町の宿では余震に起こされたり、高速道路通行料金免除の手続きで時間を余分に費やしましたが、往復1,500km、植村理事長、奥田副理事長二人のマイクロバス運転で、無事16日早朝に橿原市役所に帰ってきました。
熊本県では、まだ余震も残り、困難な事もありますが、生活できる住居が再建され、日常の平穏な生活が早期に訪れますことを願うばかりです。現地の状況により、今回のような様々な撤去の要望があったり、またひたすら泥すくいの活動や、炊き出し・避難所運営等の場合もあります。色々な要望に答えられるよう、私達も普段から努力を積み重ねて行かねばと思います。
(参加者)敬称略
防災士 植村信吉、奥田英人、村山央、末田政一、板垣伴之、北村厚司、堀内崇次、吉岡彰、川口均、板谷慶依子、
松田恵子(大坂)、南上敏明
一 般 水野智加(桜井市)、末田和子(奈良市)、奥村友宏(東京)、佐々木真奈美(東京)
<災害支援隊リーダー 防災士 南上敏明>